進路コラム「あなたには、どちらの教育が魅力的ですか?
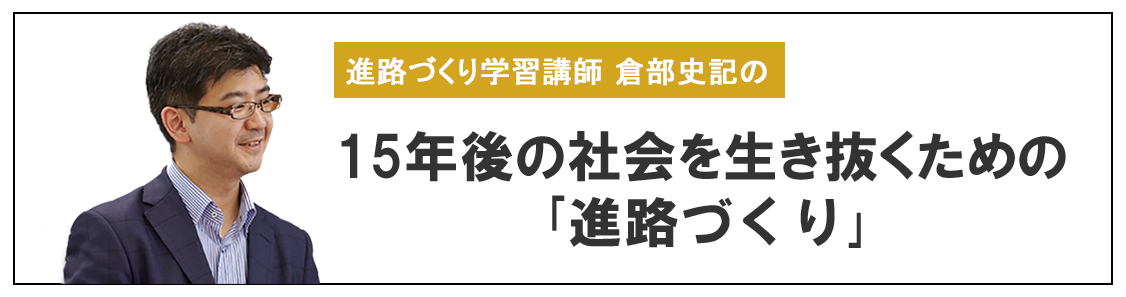
第4回 <2019年度連載>
「カリキュラム・ポリシー」から、卒業までの具体的な学びのプロセスが見えてくる
学部名や入学難易度が似ていても、4年間で修得させる資質や能力は大学によって異なります。それを受験生や社会に対して表現したものがDP(ディプロマ・ポリシー)。
2020年以降の大学入学者選抜は「自分に合った進学先とはどんな大学か」を真剣に考えることを受験生一人ひとりに求めています。そのための指針になるが各大学のDPです……と、ここまでを前回の記事「第3回 2020年度からの新大学入試①」でご説明しました。
なるほど、と様々な大学のDPをさっそく読み比べてくださった保護者の方へ伺ってみたいのですが……大学ごとの教育の違い、イメージできましたか?
正直なところ「あまり大きな違いがないように感じた」、「謳われていることはわかったが、具体的にどんな教育を受けられるかはイメージできなかった」という方もいらっしゃるのではと思います。DPはその大学・学部が目指す人材育成の「方向性」ですので、掲げる成長イメージがやや総花的だったり、他大学と似通っていたりすることもままあります。
そこで、一歩踏み込んで「どんな教育をしているか」を説明してくれるのがカリキュラム・ポリシー(CP)です。文字通り、カリキュラムがどのような目的に沿って、どのような科目群で構成されているかを示すもので「教育課程の編成・実施方針」などとも呼ばれています。
産業能率大学・経営学部を例に挙げて見てみましょう。たとえばDP(ディプロマ・ポリシー)の中に以下のような記載があります。
そして経営学部のCP(カリキュラム・ポリシー)を見てみると、以下のような記載があります。
保護者には、卒業後のキャリアについて、大学の授業で学ぶ機会などなかったという方も少なくないことでしょう。しかし現在では社会の変化を見据え、様々なキャリア教育が大学で行われています。
産業能率大学の場合、「自己のキャリア形成に対する意識を持ち、常に新しい知識や技能を学び続ける意欲」を持ってもらうことを、大学の教育目標の一つとしてDPに掲げているのですね。そして、それを学生一人ひとりにただ任せるのではなく、大学として着実に支援できるよう、様々な意図に基づいたカリキュラムや授業、学生支援の仕組みとして用意していますよ、とCPの中で発信しているわけです。DPは目指すゴール、CPはその実現のためのプロセスをそれぞれ表現しています。
2020年以降の大学入学者選抜は「自分に合った進学先とはどんな大学か」を真剣に考えることを受験生一人ひとりに求めています。そのための指針になるが各大学のDPです……と、ここまでを前回の記事「第3回 2020年度からの新大学入試①」でご説明しました。
なるほど、と様々な大学のDPをさっそく読み比べてくださった保護者の方へ伺ってみたいのですが……大学ごとの教育の違い、イメージできましたか?
正直なところ「あまり大きな違いがないように感じた」、「謳われていることはわかったが、具体的にどんな教育を受けられるかはイメージできなかった」という方もいらっしゃるのではと思います。DPはその大学・学部が目指す人材育成の「方向性」ですので、掲げる成長イメージがやや総花的だったり、他大学と似通っていたりすることもままあります。
そこで、一歩踏み込んで「どんな教育をしているか」を説明してくれるのがカリキュラム・ポリシー(CP)です。文字通り、カリキュラムがどのような目的に沿って、どのような科目群で構成されているかを示すもので「教育課程の編成・実施方針」などとも呼ばれています。
産業能率大学・経営学部を例に挙げて見てみましょう。たとえばDP(ディプロマ・ポリシー)の中に以下のような記載があります。
■ 関心・意欲
自己のキャリア形成に対する意識を持ち、常に新しい知識や技能を学び続ける意欲を持っている。
自己のキャリア形成に対する意識を持ち、常に新しい知識や技能を学び続ける意欲を持っている。
そして経営学部のCP(カリキュラム・ポリシー)を見てみると、以下のような記載があります。
◇キャリアデザイン科目
1年次から4年次までの体系的な「キャリア設計」「キャリア支援」を通じて、自己のキャリア形成に対する意識を醸成し、進路決定に資する活動を行い、社会的・職業的自立に必要な能力・態度を育成する。1年次から4年次までのゼミを「キャリア設計」の科目として設置し、進路支援を行う。「資格取得支援」により、キャリアデザインの一環として資格取得支援を行い、「初年次教育」により主体的な学びとキャリア意識を養う
1年次から4年次までの体系的な「キャリア設計」「キャリア支援」を通じて、自己のキャリア形成に対する意識を醸成し、進路決定に資する活動を行い、社会的・職業的自立に必要な能力・態度を育成する。1年次から4年次までのゼミを「キャリア設計」の科目として設置し、進路支援を行う。「資格取得支援」により、キャリアデザインの一環として資格取得支援を行い、「初年次教育」により主体的な学びとキャリア意識を養う
保護者には、卒業後のキャリアについて、大学の授業で学ぶ機会などなかったという方も少なくないことでしょう。しかし現在では社会の変化を見据え、様々なキャリア教育が大学で行われています。
産業能率大学の場合、「自己のキャリア形成に対する意識を持ち、常に新しい知識や技能を学び続ける意欲」を持ってもらうことを、大学の教育目標の一つとしてDPに掲げているのですね。そして、それを学生一人ひとりにただ任せるのではなく、大学として着実に支援できるよう、様々な意図に基づいたカリキュラムや授業、学生支援の仕組みとして用意していますよ、とCPの中で発信しているわけです。DPは目指すゴール、CPはその実現のためのプロセスをそれぞれ表現しています。


自分はどんな4年間にワクワクする?
DPが社会に対して大学が行う、大きな「宣言」のようなものであるのに対し、CPは学生一人ひとりに向けた「具体的な約束事」のようなもの。実際の大学生の中には、熱心に学ぶ学生もいれば、さぼる学生もいます。入学すれば必ず全員が同じように成長するとは限りません。でもCPに記載された授業や学習環境は、基本的にすべての入学者に対して保証されているはずです。その意味では、進学先を選ぶ受験生にとって、DPよりもさらに重みを持った内容と言えるでしょう。
CPには大学ごとの個性がにじみ出ます。ある大学のCPに「海外留学が必修」と書かれている一方で、同じ学問分野が学べる他大学では「地域と連携したフィールドワークを重視」と書かれていたりします。「自然科学、社会科学、人文科学の3領域すべてを広く学ぶこと」を求める大学がある一方で「早くから高度専門的な学問に注力できる」ことを謳う大学もあります。教養重視を掲げるCPもあれば、実践的に社会人としての実力を磨ける場であることを約束するCPもあります。
どのようなCPを良しとするかは、人それぞれ。CPは大学から学生へ提示する約束事だと前述しましたが、裏を返せば「このような教育をすることは了解していますよね」と入学者もまた問われていることになります。CPの内容を読んで「これは面白そうだな」とワクワクできるなら、あなたに合った大学の可能性が高いでしょう。イメージと違うかもと思ったら、大学案内やオープンキャンパスを通じて詳しく内容を調べてみたり、場合によっては志望校を再検討することも必要だと思います。
進学先を深く理解するヒントとして、DPとCPにぜひ注目してみてください。
CPには大学ごとの個性がにじみ出ます。ある大学のCPに「海外留学が必修」と書かれている一方で、同じ学問分野が学べる他大学では「地域と連携したフィールドワークを重視」と書かれていたりします。「自然科学、社会科学、人文科学の3領域すべてを広く学ぶこと」を求める大学がある一方で「早くから高度専門的な学問に注力できる」ことを謳う大学もあります。教養重視を掲げるCPもあれば、実践的に社会人としての実力を磨ける場であることを約束するCPもあります。
どのようなCPを良しとするかは、人それぞれ。CPは大学から学生へ提示する約束事だと前述しましたが、裏を返せば「このような教育をすることは了解していますよね」と入学者もまた問われていることになります。CPの内容を読んで「これは面白そうだな」とワクワクできるなら、あなたに合った大学の可能性が高いでしょう。イメージと違うかもと思ったら、大学案内やオープンキャンパスを通じて詳しく内容を調べてみたり、場合によっては志望校を再検討することも必要だと思います。
進学先を深く理解するヒントとして、DPとCPにぜひ注目してみてください。
(ご参考)産業能率大学の三つの方針
倉部 史記
「高大共創」のアプローチで高校生の進路開発などに取り組む。日本大学理工学部建築学科卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。私立大学専任職員、予備校の総合研究所主任研究員などを経て独立。進路選びではなく進路づくり、入試広報ではなく高大接続が重要という観点から様々な団体やメディアと連携し、企画・情報発信を行う。全国の高校や進路指導協議会等で、進路に関する講演も多数努める。著書に『看板学部と看板倒れ学部 大学教育は玉石混合』(中公新書ラクレ)『文学部がなくなる日 誰も書かなかった大学の「いま」』(主婦の友新書)など。
(ウェブサイト)https://kurabeshiki.com/
(ウェブサイト)https://kurabeshiki.com/












