
当たり前を見つめなおして
Z世代の心のツボを読み解く
経営学部経営学科 齊藤弘通 ゼミ
- #マーケティング
- #リサーチ
- #企業連携
- #プレゼンテーション
- #フィールドワーク
- #Z・α世代
ゼミ概要
齊藤ゼミでは、Z世代の価値観や行動を深く理解するためのマーケティングリサーチを学びます。インタビューや行動観察、ドキュメント分析などの定性的調査手法を駆使し、若者の本音や無意識の心理を探ります。2017年から継続している企業との共同研究プロジェクトに参加し、実践的なスキルを磨きながら、自分たち世代を客観的に分析する力を養います。また、定性調査から得た仮説を定量的に検証するアンケート調査も実施し、総合的なリサーチ能力を身につけます。「当たり前を疑い、新しい発見を生み出す」、刺激的な学びの場です。
- 研究テーマ
- Z世代の価値観と行動パターンの解明:韓国文化、企業メッセージ、自撮り行動など、多様なテーマで定性的調査手法を用いたマーケティングリサーチの実践
- ゼミの特徴
- 企業との共同研究で実践力を磨く、Z世代による Z世代の分析、創造的な問題解決力の育成
- 主な活動
- 食品メーカーと連携したマーケティングリサーチプロジェクト、定性的調査手法の習得(インタビュー、行動観察、ドキュメント分析)、チームでの調査研究活動、中間報告と最終報告を通じた研究成果の企業への報告
- ゼミ生の進路
- マーケティングリサーチ会社、一般企業の企画・マーケティング部門などを中心に様々な業界
| 個人ワーク | 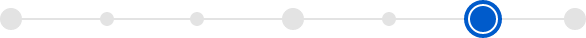 |
グループワーク |
| 学内活動 |  |
学外活動 |
| 理論 | 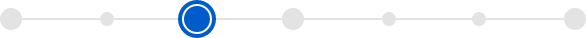 |
実務 |
齊藤ゼミ3つのキーワード
-
Z世代の心を読み解く
探検家に齊藤ゼミでは、Z世代の学生たちが自分たち自身を研究対象として、新たな視点で自己を見つめ直します。当たり前だと思っていた日常的な行動や価値観を、一歩引いた視点から観察し、その背景にある心理を探ります。インタビューや行動観察、ドキュメント分析などの手法を用いて同世代の深層心理に迫ることで、自己理解を深め、客観的な分析力と洞察力を磨いていきます。
-
インサイトを明らかにする
マーケティングの最前線大手食品メーカーとの共同プロジェクトに参加し、「なぜ韓国コスメが人気なのか」「なぜ自撮り行動をするのか」、などのZ世代の行動の背景にある感覚や心理、価値観を調査します。4つのチームに分かれて研究を行い、中間報告と最終報告を企業に対して実施します。様々な切り口からZ世代の日常を調査し、インサイトを明らかにすることは、未来の市場を予測するマーケティングの最前線と言えます。
-
「みえないものをみる」
センスを磨く当たり前を「当たり前」と捉えずに、疑い、深く考え抜く能力は、マーケティングだけでなく様々な分野で活かすことができます。 「なぜ?」と問い続ける姿勢は、新たな発見や創造的な解決策を生み出す源となります。多角的な視点で物事を捉える力は、社会人になってからも、複雑な課題に柔軟に対応する助けとなります。こうした洞察力と創造力を備えた人材になるための基礎力・応用力を身に付けていきます。
カリキュラム
2年生
マーケティングリサーチを基礎から学ぶ
調査法の基礎を学びつつ、チームに分かれ、 初めてのマーケティングリサーチに挑戦します。定性的調査手法(インタビュー、行動観察、ドキュメント分析)を習得し、企業から提示されたテーマに基づいてチームでリサーチを行います。マーケティングリサーチプロジェクトⅠとして、Z世代の価値観や行動を探り、中間報告と最終報告を企業に対して行います。優秀チームは企業訪問の機会も得られます。
3年生
実践的なリサーチスキルの向上を目指す
前期はマーケティングリサーチプロジェクトⅡ、後期はⅢを実施します。企業との協働でより複雑なテーマに取り組み、定性調査と定量調査を組み合わせた総合的なリサーチを行います。後期には自らテーマを設定し、独自の視点で調査研究を進めます。企業への報告会を通じて、プレゼンテーション能力も磨きます。優秀チームは産能祭でポスター発表を行います。また3年次のリサーチプロジェクトにおける優秀チームも企業訪問の機会が得られます。
4年生
Z世代研究の集大成
これまでに習得したリサーチスキルを活かし、「Z世代の行動の背後にある感覚や価値観を探ること」を課題として個人研究またはペアでの研究を行います。先行研究を調べ、独自の研究課題を設定します。毎週の進捗報告と教員からのフィードバックを通じて研究を深め、7月にゼミ内で研究発表を行います。優秀な研究は秋の産能祭でポスター発表の機会があります。
カリキュラムは変更になる場合があります。
ゼミの取り組み
食品メーカーとの共同によるマーケティングリサーチ
2年生から3年生にかけて、大手食品メーカーとの共同研究プロジェクトに参加し、Z世代の消費者インサイトを探ります。企業から提示されたテーマに基づき、Z世代の価値観や行動を調査研究します。研究結果は企業へ報告を行い、実際の商品開発やマーケティング戦略に活かされます。

韓国コスメが人気の理由を調査
調査活動は4つのチームに分かれて行います。韓国コスメが人気の理由、自撮り行動の心理、企業メッセージの受け止め方など、興味深い研究テーマに対して、インタビュー、行動観察、ドキュメント分析などの手法を用いて多角的に分析します。チームで調査することにより、多様な視点を学びコミュニケーション力も磨かれます。

インサイトを探り出す質的調査
インサイトとは、「洞察」や「見抜くこと」といった意味合いの言葉で、マーケティングにおいては、消費者の購買行動の背後にあるホンネや隠れた欲求、動機を指します。ゼミではチームに分かれ、調査を通じて得た消費者の定性データから消費者のインサイトを読み解く研究を行い、消費者のツボに刺さるマーケティング施策を立案します。
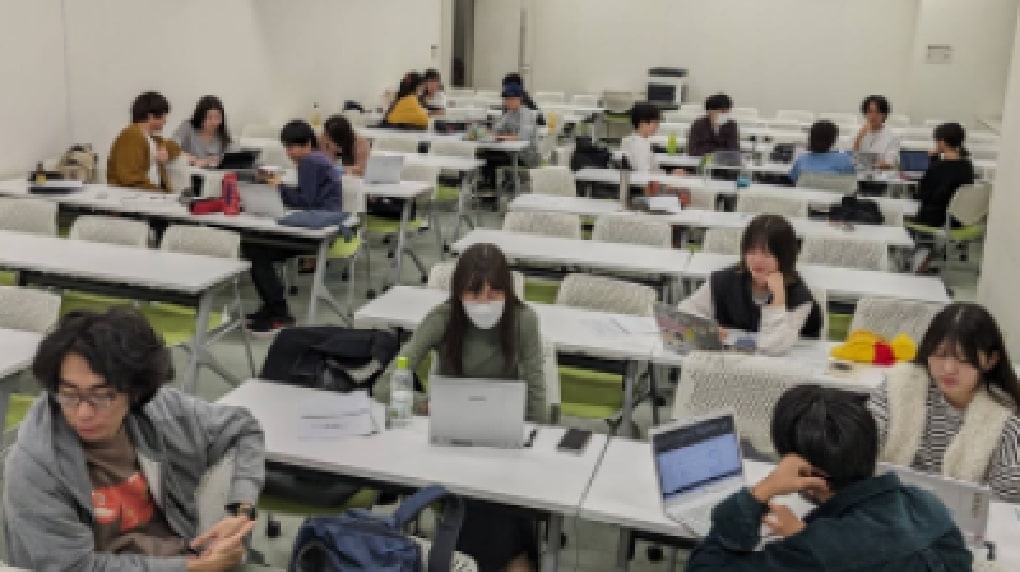
「みえないモノをみる」センスを磨く夏合宿
夏休みに1泊2日のゼミ合宿を行います。集中的に調査活動や分析作業に取り組むことで、研究の効率とチームの結束力を高めます。また、ゼミ生同士の交流が深まり、異なる学年の経験や知識を共有することで、ゼミ全体の研究レベルを向上させる貴重な機会にもなっています。

学生によるゼミ紹介
Z世代が「Z世代の思考」を探り、社会に貢献する

請地 和香
私立大成高等学校出身
「Z世代の思考」をZ世代自ら客観的に調査する研究を行っています。ゼミ活動では、企業様から提示された課題に対して研究を行いました。Z世代のインサイト探索のため、インタビューやアンケートを中心に調査を行い、Z世代の価値観・ワードチョイスにこだわったことで充実した調査結果を得ることができ、企業様からも評価をいただきました。ゼミでの研究により、普段何気ない生活に潜む「ツボ」を探し出すため、日々価値観アンテナを張ることが当たり前となり、学生生活や人間関係にも役立っています。
マーケティングリサーチを学び、見えない価値を探す旅

梶川 碧生
私立淑徳巣鴨高等学校出身
博識でユーモアのある先生の下、マーケティングリサーチを学んでいます。ゼミ生は研究熱心で好奇心旺盛、「なぜ」を追求し楽しく真面目に取り組みます。皆が見えない価値を言語化するワードメーカーで、意見しやすいアットホームな環境の中、自分らしく学び成長できます。 “見えないモノを見る”って不思議です。私は性格や美容診断の価値を調査しており、見えない価値を引き出すリサーチの面白さに日々ワクワクしています。「疑問」から生まれる「知りたい」の思いが学びの活力に。私たちのインサイト探索の旅に終わりはありません。
学生に期待すること

探究は、当たり前を見つめ直すところから始まります。常識や既成概念に疑問を投げかけ、徹底的に「なぜ?」に向き合ってみませんか?当ゼミでは、企業と共同しZ世代の若者の価値観や行動様式についてリサーチし、リサーチペーパーをまとめる活動を行っています。マーケティングリサーチは定性・定量両面から、人々の内面にある動機や感情を探り、社会の新しいトレンドを見出す創造的な活動です。固定観念にとらわれない柔軟な思考を持ち、視野を広げ、洞察力を磨いていきましょう。そしてここで得た経験を経て、将来世代を超えて理解し合う環境を作り、みんなで支え合う社会を作る役割を担える人材になって欲しいと思います。
齊藤 弘通 教授
慶應義塾大学文学部人間関係学科教育学専攻卒 、法政大学大学院政策科学研究科修士課程修了 、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了 、学校法人産業能率大学総合研究所を経て、産業能率大学 経営学部教授
【教員紹介】齊藤 弘通 教授 ページへ















