進路コラム「高校1〜3年生、それぞれにお勧めの、3月の過ごし方」
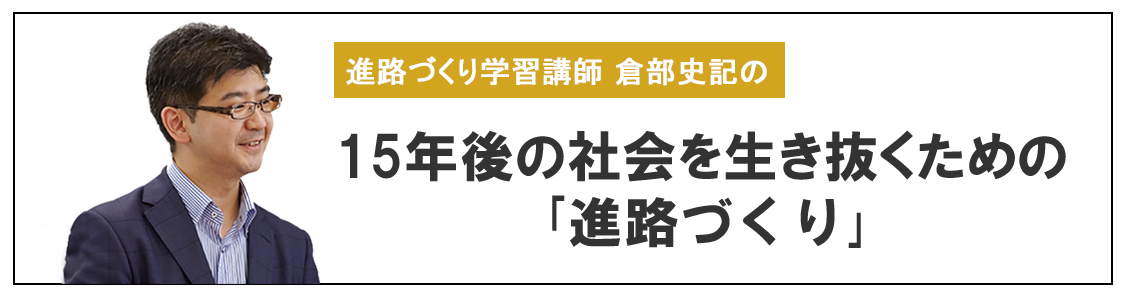
第6回 <2024年度連載>
①合格を得た受験生にお勧めのアクションは?
2月は私立大学の一般選抜が集中する時期です。本コラムを目にされた時点で、既に合格を得たご家庭もあるのではないでしょうか。
このタイミングで知っておいていただきたいことを、昨年のコラムでご紹介しました。よろしければ以下を先に読んでいただければと思います。
特に複数の大学から合格を得た場合の「最後は本人が自分の意思で選ぶこと」という点は毎回、強調したいところです。規模の大きい伝統校の方が就職では有利だろう、○○大卒がウチの会社では高く評価されている……等々、つい意見を言いたくなる瞬間もあろうかと思いますが、学ぶのは保護者ではなく本人。お子さんがその選択を後悔しないかどうかを大事にしてあげてください。
合格を得た大学の大学案内やウェブサイトを、親子でいま一度チェックしてみるのも良いですね。受かった後だからこそ見えてくる点もあるはず。疑問点や気になる点があるなら、大学に問い合わせて確認しましょう。既に進学先を決めている方にとっても、モチベーションを上げる良い機会になると思いますよ。
ちなみに、キャンパスにもう一度、足を運んでみるのもお勧めです。大学入学共通テスト利用入試などをはじめ、一度も訪問したことがない大学に合格するケースは、一般選抜では珍しくありません(ただし入試の実施日等はキャンパスに入れないことも多いので、事前に確認を)。
無事に進学先を決め、入学手続きや授業料などの手配もすべて済ませたなら、少し気持ちに余裕ができますね。進学を控えたご本人も春からの学びを楽しみにされているかと思いますが、新生活を始める春には危険も潜んでいます。
たとえばお子さんは「#春から○○大」なんてタグを付けた投稿をSNSでしていませんか? こうした投稿が、怖い勧誘などに繋がるケースもあるようです。危険を回避する方法というのも、大人になる過程で必要な学びと思います。良き出会いを心から楽しむためにも、必要な注意喚起を保護者の方からぜひ。
②1、2年生にとっては進路検討の大事なチャンス!
高校2年生、1年生の皆様にとっても、3月は進路のことを考える大切な時期ですね。
様々な大学や専門学校の教職員を高校に招いて行われる「出張説明会」が、多くの高校で開催されます。春休みにオープンキャンパスを実施する大学も結構、多いんですよ。
特に高校2年生の皆様。総合型選抜や学校推薦型選抜を検討されているのなら、志望校のリサーチは春のうちにスタートされることを強くお勧めします。こうした入試では「なぜ同じ分野を持つ他大学ではなく、この大学で学びたいのか」という学校理解を深めることが大切。その情報収集を3年生の夏から始めようとすると、出願書類を練り上げるためのスケジュールに少々、余裕がなくなってくるのです。
第一志望校はもちろんですが、併願先になりそうな大学のことも詳細に調べましょう。授業スタイルや教育理念、カリキュラム、就職先、学費等々……様々な観点で比較検討することにより、各大学の特色の違いが見えてきます。
漫然と話を聞くのではなく、「こうしたテーマを学びたいのだけど、ここで学べるか」「この職業に就職する方はどれくらいいるのか」等、自分が気になる点を事前に準備しておき、相談ブースなどで積極的に確認を。得られる気づきや情報の深さが大きく違ってきます。
4月からは、高校の授業も「受験生モード」に切り替わります。模試を受ける頻度も上がりますし、三者面談では具体的な志望校について話し合われることも。総合型選抜などを検討する場合、そこに向けた指導も始まっていきます。進路関係の行事が一気に進みますので、3月のうちに先を見越して動いておいた方が、慌てずにモードを切り替えられるはずです。
高校1年生なら「何を学びたいか」という、学問や職業についての理解を深めることが大事ですね。この時期なら既に文理選択を終えた高校生が多いと思いますが、たとえば文系の中にも様々な学問があります。
文学や歴史学、哲学のように人間の内面を探究する人文科学と、法学や経済学、経営学のようにより良い社会の仕組みを探究する社会科学とでは、研究する対象もアプローチも違います。経済学と経営学も、字面こそ似ていますが、4年間のカリキュラムには結構な差が。後悔しないためには、やはり比較が大事です。
「私は○○学にしか興味がないから」と狭い範囲に固執するのではなく、まずは広い範囲で様々な学問の話を聞くことをお勧めします。率直に言って、高校生が進路について知っている知識は多くの場合、やはりごく狭い範囲に限られていると思うのです。だからこそ、たった20分程度の話が将来の夢を見つけるきっかけになった、なんてことも珍しくありません。
オープンキャンパスなら親子で参加できますが、高校で行われる学校説明会は本人のみ。どんな機会もすべて、「何を知るために、その場に参加するのか」という心構えを持って臨むようにしましょう。
中だるみしがちな時期だからこそ、この時期を濃密に過ごせるかどうかで、その後の動きが変わってきます。ぜひ、充実した日々を送っていただければと思います。
倉部 史記
進路指導アドバイザー。北海道から沖縄まで全国200校の高校で生徒・保護者向けの進路講演を実施。各都道府県の進路指導協議会にて、高校の進路指導担当教員に対する研修も行う。多くの大学で入試設計や中退予防、高大接続についての取り組みを手がける。三重県立看護大学高大接続事業・外部評価委員、文部科学省「大学教育再生加速プログラム(入試改革・高大接続)」ペーパーレフェリーなど、公的実績も多数。
日本大学理工学部建築学科卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。私立大学専任職員、予備校の総合研究所主任研究員などを経て独立。著書に『大学入試改革対応! ミスマッチをなくす進路指導』(ぎょうせい)など。
(ウェブサイト)https://kurabeshiki.com/
日本大学理工学部建築学科卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。私立大学専任職員、予備校の総合研究所主任研究員などを経て独立。著書に『大学入試改革対応! ミスマッチをなくす進路指導』(ぎょうせい)など。
(ウェブサイト)https://kurabeshiki.com/












