経営学部 基礎科目
SANNOは基礎科目から面白い!
マーケティング論

また、カスタマーリレーションシップ(お客様との関係構築)やカスタマーインサイト(消費者心理)、ブランド構築などについても学習し、未来志向でマーケティングを考える視点を身につけます。数多くの具体的な事例に触れながら、消費者として商品・サービスに接してきた経験をマーケティング的な視点から捉え直し、マーケターになるための一歩を踏み出します。
日頃から「なぜ売れるのか」を考えて商品やサービスを利用するようになりました
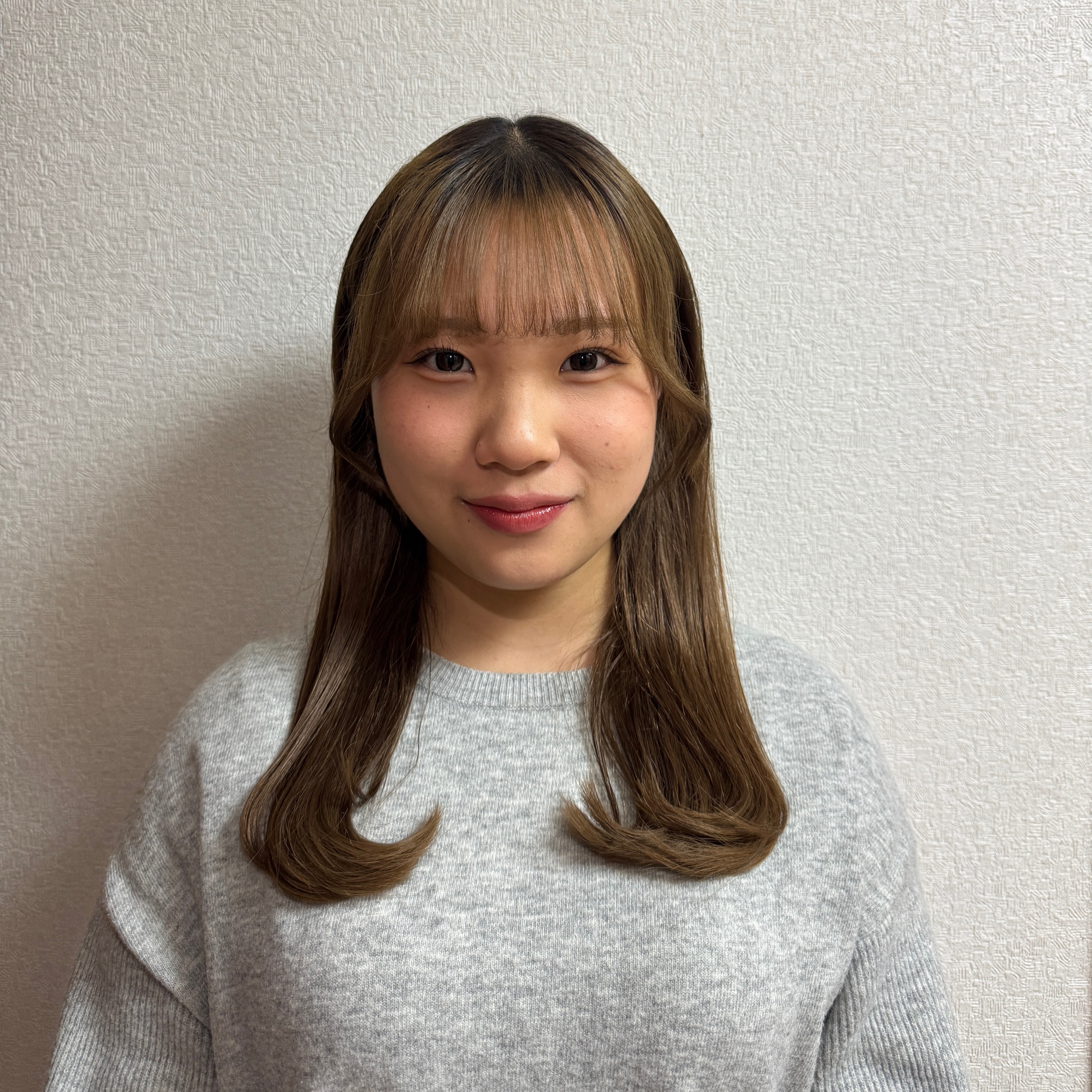
植松 優衣 静岡県立三島南高等学校出身
Q.この授業の魅力は?
商品が売れる仕組みや、消費者の心理を学べる学問として、マーケティングに興味をもったことが入学の動機です。しかし、当初は漠然としたイメージしかありませんでした。この授業の魅力は、そもそも「マーケティングとは何か」という概念から学習を始められる点にあると思います。
また、知識として覚えるだけではなく、分析や考察を通して理解を深める演習にも取り組みます。身近な企業の商品サービスを題材に、採用されている戦略や施策を調べるグループワークなども行うので、1年次の授業の中で一番楽しい時間でした。
Q.授業で得た気づきや発見は?
印象に残っている授業のテーマは「ターゲット市場の設定」です。それは、同時進行する初年次PBLの中で判断に迷い、難航したパートでもありました。授業で学んだSTP分析※の手法を、マーケティング戦略の立案に活かしたことで、効果的かつ根拠のある課題解決策にまとめることができました。
授業を通して見えてきたのは、「誰に何をどのように届けるか」という売れる仕組みです。それを日頃から考えて商品サービスを利用するようになりました。
将来は、マーケティングを学ぶ中で発見した価値観や視点を役立てられる仕事に就きたいと思っています。
※STP分析:Segmentation(市場の細分化)、Targeting(狙うべき市場の決定)、Positioning(自社の立ち位置の見極め)を行うための手法
ビジネスモデル論

顧客の目線で商品サービスを創り出すための発想力や分析力が養われました

宇津城 宙緯 東京都私立品川翔英高等学校出身
Q.この授業の魅力は?
アパレル、外食、ネットビジネスなど、幅広い業界のビジネスモデルを実例にもとづいて学ぶことができます。企業がどんな顧客ニーズに注目し、どのような価値を提供しているのか。知識を覚えるのではなく、目の付け所や発想法を学べる点に魅力があると思います。印象に残っているのは、ビジネスモデルを視覚化する演習です。ヒト・モノ・カネ・情報の流れや取引を関係図に表し、分析ソフトを駆使して提供される価値を明らかにしていきます。自ら考察してアウトプットすることで、利益を生むしくみを深く理解することができました。
Q.授業で得た気づきや発見は?
発見が多かった要因は、経営学科とマーケティング学科の共通科目であることも大きいです。ビジネスモデルの分析などに取り組むグループワークでは、在籍学科の違いも個々の見解に表れ、学び合うことで多くの分析視点を得ることできました。授業を通じて気づいたのは、ビジネスモデルとは真似れば成功する法則ではないということです。顧客ニーズや環境の変化に応じて変革を続けてこそ、ビジネスは持続可能になることを学びました。授業で養われた発想力や分析力を、今後は企業とコラボレーションするPBLなどに活かしたいと思います。
会社のしくみ

具体的にまず、会社の組織構造について学びます。主要な会社形態(合同会社, 株式会社など)、経営戦略と組織体制の関係、経営に求められるガバナンスなどについて学習します。つぎに、会社の活動を支える人的資源に関して雇用形態や職種、会社を取り巻く規制および社会的要請(ダイバーシティ, SDGs, ESGなど)について学んでいきます。さらに、動画教材やカードソート、ロールプレイ、ケーススタディ、グループワークなど多様な学習形式を経験しながら、SANNOスタイルの学び方も身につけます。
会社を見る眼が養われ、興味のある業界や仕事も見つかりました

渡邉 玲乃
埼玉県立川越南高等学校
Q.この授業の魅力は?
講義で終わらない授業形式も魅力の一つです。ペアやグループで取り組むワークや、ゲーム形式で楽しく学べる演習もあり、能動的に学習できました。ステークホルダー(会社の利害関係者)について学ぶ授業では、当事者になりきって会社経営をめぐる利害の対立をロールブレイ形式で体験し、関係性を実感することができました。
Q.授業で得た気づきや発見は?
SDGsやCSR(企業の社会的責任)が経営にどんな影響を与えるのか。今なぜ企業はパーパス(存在意義)の言語化や浸透に注力しているのか。企業の事例を題材に学んだことで、社会に対する関心も高くなりました。
一番の収穫は、さまざまな職種(営業、企画、人事など)の存在を知ったことです。働く人のインタビュー動画を視聴しながら、職種による役割の違いや必要なスキルを知ることができました。この授業を受けたことで、以前は注目していなかった業界や仕事に興味をもち、今後はもっと研究しようとモチベーションが上がりました。
財務諸表論

また、企業研究を目的としたIRデータ(有価証券報告書やIR動画)の定性情報の見方も学ぶことで、論理的思考力の強化を図ります。
この授業で得た知識は、4年間の学びの基礎となるのみならず、就職活動で会社を選ぶ際などに、今後成長する会社かどうかを見抜く第1歩つながるなど、ビジネスの世界に出てからも有用です。
数字が変化した背景まで読み解けるようになり、将来の起業に向けた第一歩になりました
加舎 由理奈 東京都私立三田国際科学学園高等学校出身
Q.この授業の魅力は?
財務諸表と聞いても当初はイメージが湧きませんでしたが、授業が進むにつれて学習が面白くなりました。貸借対照表は“お金の使い方”、損益計算書は“家計簿”と捉え、経営状況を数字やデータから把握できるようになっていったからです。
有名企業の財務諸表を題材に取り組む演習中心の授業であることや、経営や財務の実務経験をもつ先生の丁寧な解説により財務諸表の見方をスムーズに理解することができました。“経営にどう役立てるか”を学ぶ授業なので、数字や計算問題が苦手な人でも意欲的に受講できると思います。
Q.授業で得た気づきや発見は?
財務諸表の見方を理解したことで、企業の売上や利益の背景にまで意識が向くようになりました。この視点は、就職する企業を研究する際にも活かせると思います。また、財務諸表から経営状況を判断する中で、論理的な思考力も養われました。
卒業後の目標は、好きな音楽業界に携わり、将来的には起業することです。持続可能なビジネスを営み、会社を長く存在させるには、経営状況を自ら把握する必要があります。その第一歩として、この授業で学んだことは大きな価値があり、経営的な視点を身につけることができました。
















