
私の視点 2021
ビジネスの力で、地域を支える 人口減少社会と向き合う卒業生の今
~SANNO教員×卒業生 対談~
日本が直面する人口減少という社会課題。そんな大きなテーマと真正面から向き合い、シニアサポート事業を展開するMIKAWAYA21株式会社の花家和明さん(2014年卒)。地域が抱える課題を解決するには、どんなアプローチが有効なのか。SANNOでの学びを、どのように活かしているのか。恩師である松尾尚教授との対話を通じて、その視点に迫っていきます。
 松尾
松尾経営学部教授の松尾尚です。経営戦略やマーケティング理論を教えています。今日は僕のゼミの卒業生である花家さんにお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いします。
花家和明です。MIKAWAYA21株式会社というベンチャー企業で働いています。
 花家
花家 松尾
松尾早速だけどMIKAWAYA21は、どんな事業を手がけている会社なの?
地方の中小企業と提携して、高齢者の方々の困りごとを解決する「まごころサポート」という事業を展開しています。僕は主に営業として、地元企業と高齢者の方々をつなぐ橋渡し役を担っています。
 花家
花家 松尾
松尾「地方」も「高齢者」も、これからの日本でビジネスをしようと思ったら、避けては通れないテーマだからね。そのあたりも、今日はじっくり聞かせてください。

地元企業とともに、シニア世代の困りごとを解決していきたい
 松尾
松尾花家さんは、卒業して最初は広告代理店に就職したんだよね?
SANNOで学んだマーケティングのスキルをダイレクトで活かせると思い広告代理店に入社しました。新聞折込チラシを扱う広告代理店で、二年ほど働きましたね。
 花家
花家 松尾
松尾転職を考えたのは、何かきっかけがあったの?
代理店で働くかたわら、友人に誘われて福井県の鯖江市で行われていた地方創生のイベントに参加したんです。その集落では、70代のおじいさんが「最年少」で、その方がさらに高齢のお年寄りたちの生活を支えている状況。少子高齢化が限界まで進んだ集落の厳しい現実を目の当たりにして、衝撃を受けました。
 花家
花家 松尾
松尾東京にいると、ちょっと信じられない光景だけど、それが今の地方の“リアル”なのかもね。
僕も「この問題は鯖江だけのものではない」と感じました。少子高齢化が進むなか、行政の支援やボランティアだけでは限界があります。地域の課題に対して持続的にサポートをするためには、ビジネスとして収益を得る仕組みが必要になってきます。そんな良い循環を実現している企業がないか調べていくなかでMIKAWAYA21に出会ったんです。
 花家
花家 松尾
松尾「まごころサポート」では、具体的にどんなサービスを提供しているの?
電球の交換から、部屋の掃除、リフォーム業者の紹介まで、何でもござれです。サザエさんでいう三河屋のサブちゃんみたいなイメージで、地域の御用聞きというか、気軽になんでも相談できるコンシェルジュのような存在を目指しています。
 花家
花家 松尾
松尾なるほど。だから「MIKAWAYA」なのか。
行政のサービスだと、どうしても範囲が限定的になってしまいますが、高齢者の方もサービスを選びたい。「まごごろサポート」は、地域の新聞販売店や地元企業と提携しながら、そうしたニーズに応えています。
 花家
花家 松尾
松尾けっこうアナログな印象だね。
実はそこが僕たちの狙いなんです。デジタル一辺倒の世界になると、高齢者の方々がどうしても置いてきぼりになってしまう。だから僕たちは、テクノロジーの力を活用しつつも、アナログな価値観を持ち続けていきたいと考えています。
 花家
花家 松尾
松尾なるほど。ちなみにテクノロジーの力は、どんなシーンで活用しているの?
自社で高齢者の方との「会話」をデータとして蓄積しているんです。それをAIによって分析することで、マーケティングの精度を高めています。
 花家
花家 松尾
松尾すごいね。そんなことしている企業、ほかにないんじゃないかな。
シニア向けマーケティングには力を入れていますし、大企業にもひけをとらない自信があります。
 花家
花家
ビジネスの基礎からコミュニケーションまで、大学で身についたこと
 松尾
松尾SANNOで学んだことが活かされていると感じることはある?
それはもう、たくさんあります。営業の戦略などを考えるときには、先生に教えてもらったさまざまなフレームワークが役に立ちます。あとは授業で学んでおいて良かったと思うのは、ガントチャート(※)のつくりかた。とても重宝しているスキルです。
 花家
花家 松尾
松尾ガントチャートづくりは、プロジェクトマネジメントの基本だよね。授業で身につけたことが、ビジネスの現場でも活きているのなら、私たち教員としてもうれしいな。
SANNOではゼミをはじめとして、グループで取り組む課題が多かったので、コミュニケーション能力も自然と磨かれた気がします。
 花家
花家 松尾
松尾花家さんは、在学中本当にいろんな活動に積極的だったよね。
たくさん経験させてもらいました。例えば、他大学の学生と協働したビジネスコンテストに参加させてもらったり、SANNOの学生に学びの場を提供するサークル「SHU-HA-RI」を立ち上げたり。あとは、ゼミの一環で東京タワーの経営分析を独自で行い、社員インタビューをさせてもらったのも印象深いです。
 花家
花家
 松尾
松尾僕のゼミでは、ゼミ長としてもがんばってくれていたよね。個性的なメンバーをまとめつつ、いろんな活動をして、なかなか大変だったんじゃない?SANNOは多くの企業とつながりがあるけど、君たちは、あえて自分たちでアポ取りから何までやっていたわけだから。
そうやって自分からいろいろなところに飛び込んで、さまざまなバックグラウンドを持った大人たちと関われたことは、本当に得がたい経験だったと思います。 相手の多様性を受け入れながら、自ら考えてプロジェクトを進めていく術を、大学で身を以て学べた気がします。
 花家
花家損得を越えたところに、ビジネスの醍醐味がある
 松尾
松尾仕事をしていて一番やりがいを感じるのはどんなとき?
パートナーである地元企業の皆さんと一緒になって、地域の課題解決に本気で取り組んでいると実感できたときですね。地元企業の皆さんも、地域に恩返しをしたいという思いのある方が多いから、単にビジネスとしての付き合いを越えた信頼関係が築けるというか。そこもこの仕事のおもしろさです。
 花家
花家 松尾
松尾企業としての営利活動と社会貢献とが、矛盾することなく両立している。でも、しっかりと信頼関係が築けているのは、花家さんの人柄もあるんじゃないかな。僕も君のことは、歳の離れた友人のように思っているところがあるもの(笑)。
先生にそう言ってもらえるのは、素直にうれしいです!
 花家
花家
 松尾
松尾ちょっと褒め過ぎちゃったかな。でも、僕が一度だけ花家さんに怒ったことがあったでしょう?
僕が松尾先生の授業の時間をちょっとだけお借りして、イベントの宣伝をしたいとお願いしたときのことですよね。せっかく先生が時間をくれたのに、うっかり時間を間違えてしまって……。
 花家
花家 松尾
松尾そうそう。悪気はないのはわかっていたから、怒らなくても良かったのかもしれないんだけどさ。でもそれってつまり、花家さんへの信頼の裏返しでもあるんだよ。
社会人になって改めて実感するのですが、やっぱり約束を守るって、人としての基本じゃないですか。だから今も、あのときの反省を忘れないようにしています。
 花家
花家
SANNOでの出会いが、きっとキャリアの糧になる
 松尾
松尾これからSANNOに入ってくる高校生に、伝えたいことはある?
大学の4年間は、人生のなかでもすごく特別な時間だと思います。だからこそみんな進路に悩むと思うのですが、「SANNOだったら間違いない」ということだけは自信を持って伝えたいです。経験もそうですが、ここでの出会いが今の僕をつくってくれた。将来子どもができたら、SANNOを薦めたいです。
 花家
花家 松尾
松尾ちなみに花家さんは、高校生のときに思い描いていた未来と、今の自分の姿は重なっていると思う?

まさか自分がベンチャー企業で働いたり、地方で暮らすシニアの方々のサポートをしているなんて、考えてもみませんでした。それに就職してからも、決して順風満帆というわけではなくて。大人になってからも、迷ってばっかりです。
 花家
花家 松尾
松尾そういうときは、どうするの?
悩んだり迷ったりしたときは「松尾先生やSANNOの仲間に、胸を張って会える自分であるか」考えることが多いですね。あとはやっぱり、人と話してみることでしょうか。一人で悩んでいても、答えがでないことってたくさんありますから。幸いにも、今は自分が心からやりたいと思える仕事ができていますが、それも自分で選び取ったというよりも、いろんな人との出会いが重なったおかげだと思うんです。
 花家
花家
 松尾
松尾そういうのをキャリア理論だと、計画的偶発性理論(プランド・ハプンスタンス)と呼ぶんだよね。明確にキャリアプランを描いていなくても、「こういう風になりたいな」と思いながら、好奇心を持っていろんなことに接していくと、自然と自分の望むキャリアに辿り着ける。だからSANNOの学生も、これから入学してくる高校生も、とにかくいろんな物事にぶつかってみてほしいなと感じています。
ゼミの同期が海外留学を決めたときに、みんなで色紙を書いたじゃないですか。あのとき、松尾先生が書かれていた言葉が、僕はすごく好きで。「月に手を伸ばせ。たとえ届かなくても」。大事なのは、手を伸ばすことなんですよね。これからSANNOで学ぶみなさんも、届かないことを恐れず、自分なりの月に向かって、手を伸ばしてみてください。
 花家
花家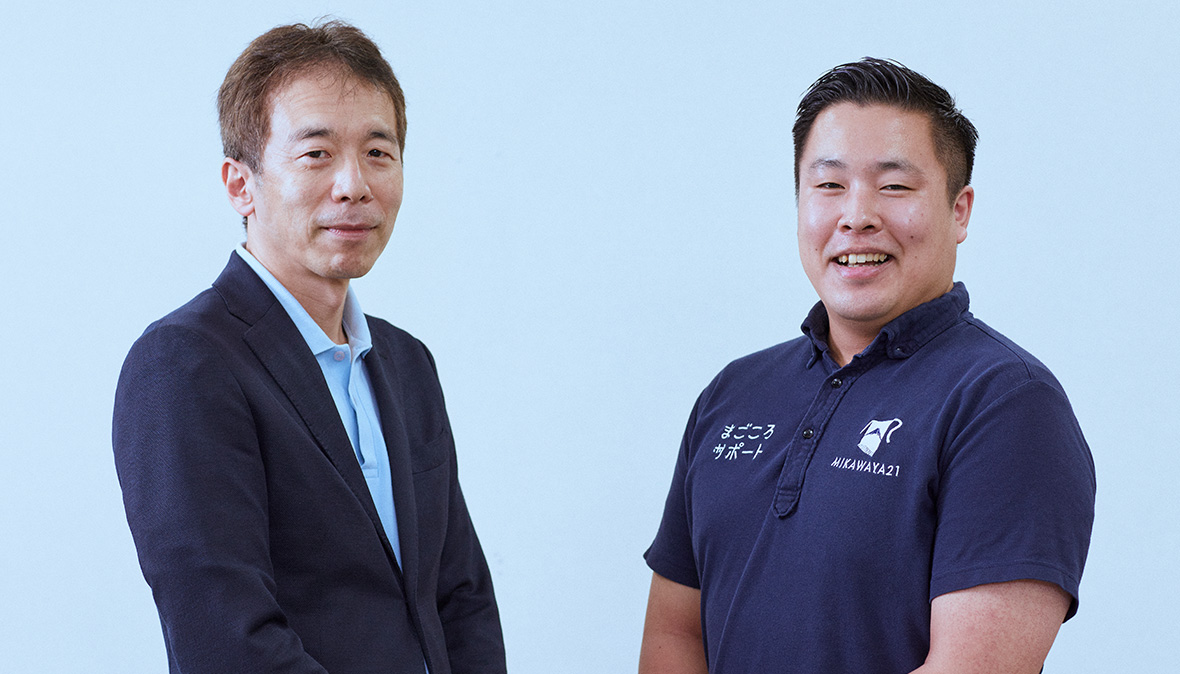
プロフィール
-

-
花家 和明 HANAIE KAZUAKI
MIKAWAYA21株式会社
2014年に経営学部現代ビジネス学科(現 経営学科)を卒業後、広告代理店を経て、2017年にMIKAWAYA21株式会社に中途入社。新聞販売店向けに「まごころサポート」の新規開拓営業を担当する。その後、経営企画部門やカスタマーサクセス部門で経験を積み、現在は、新規開拓営業を担当しながら、東京都荒川区に出店する直営店「まごころサポート荒川本店」の店長も勤める。
-

-
松尾 尚 MATSUO TAKASHI
経営学部教授
総合電子部品メーカーの村田製作所にて、マーケティング戦略や新規事業育成、M&Aなどの経営企画業務に携わった後、本学経営学部の教授に就任。マーケティングや経営戦略の理論的枠組みに、前職での経験を加えることで、実際のビジネスの現場でも通用する「生きた学問」を伝えていくことを目指す。
















