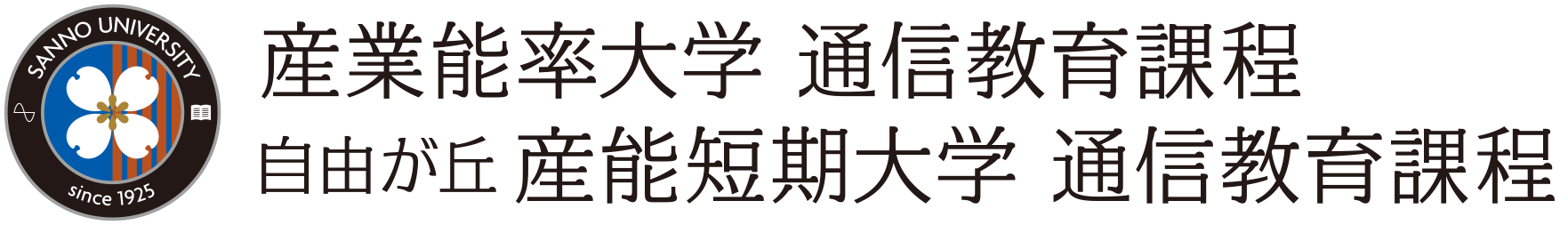リレーエッセイ 2021.06

松本 久良 (Hisanaga Matsumoto)
<担当科目>
「組織マネジメント論」「経営戦略論」「経営学入門」他
<趣味、特技等>
トレーニング、歌唱、ダンス、スイム など
<メッセージ>
乱気流時代の経営などと言われて久しいですが、最近はさらにコロナ禍によって混沌さが増してしまいました。こんな中を企業もそして個人も生き残っていかなければなりません。今は学生としてあれこれと考えるチャンスです。
本学での学修を通して、それぞれ関心のある分野での専門性とともに、厳しい時代を生き抜く術をつかんで欲しいと思います。
「組織マネジメント論」「経営戦略論」「経営学入門」他
<趣味、特技等>
トレーニング、歌唱、ダンス、スイム など
<メッセージ>
乱気流時代の経営などと言われて久しいですが、最近はさらにコロナ禍によって混沌さが増してしまいました。こんな中を企業もそして個人も生き残っていかなければなりません。今は学生としてあれこれと考えるチャンスです。
本学での学修を通して、それぞれ関心のある分野での専門性とともに、厳しい時代を生き抜く術をつかんで欲しいと思います。
ようこそ、経営学の世界へ
産能通信教育で学ぶみなさんこんにちは。松本久良(まつもと ひさなが)と申します。経営学関連の科目を担当させていただいております。今回みなさんに向けて自己紹介も兼ねたお話を差し上げるということで、気の利いたお話ではありませんがお付き合いください。
学生時代から経営学を学習してきましたが、最初の産能との出会いは短期大学でした。それは今から27年ほど前に遡ります。私もまだ若く少年の面影を残していたに違いないでしょう。「あれから40年」、いや27年ですが、今では残酷な時の彫刻によって見事なオヤジへと変貌を遂げました。それはさておき、短大では若い学生さんはもちろん、社会人学生の方も多く学ばれており、多くのことを共に学ばせていただいたと思っています。
そしてその翌年から、通信教育課程(大学・短大)でお世話になるようになり、それまで以上に社会人の学生さんを中心に授業を行うようになりました。爾来、通信教育課程でも26年間、「文武両道」ならぬ「文勤両道」(勝手な造語ですが勉強と仕事の両立の意)を目指す学生さん、そして献身的にサポートしてくださる事務部の方々、みなさんのおかげで現在まで続けてこられたと感謝しております。私の心身共に「MADE IN SANNO」と言えると思います。
私の身の上話などはこのへんにして、経営学関連を学ぶ学生さんも多いと思いますので、次に少々真面目に経営学の歴史を彩ったその時々の主要なテーマを超コンパクトに概観してみたいと思います。
近代経営学(アメリカ経営学)の本格的な萌芽はF.W.テイラーの「科学的管理法」に見出せると言われています。これは、当時の工場でのいい加減な「成り行き的な管理」から脱却するために、工場での仕事を科学的に分析し作業者に割り当てることで、ムダをなくし生産性を向上させようということに主眼が置かれます。これを「効率探求の時代」(おおよそ19世紀終わりから20世紀初頭)と呼ぶことにしましょう。これが第1ステージで「管理論」から経営学はスタートしました。
ちなみに、わが国における「マネジメント」思想の始祖は本学の創立者上野陽一先生です。先生は海の向こうの「科学的管理法」の思想にインスパイヤ—され、その考え方をさらに日本流に発展させ「能率学」として日本マネジメント界の原点を開花させました。そして、管理の理想形として、ムダもムリもないムラのない状態、明確な目的とそれに適合した手段がとられている状態、持ち前が100%発揮されている状態、などに着目しました。すなわち、能率を実現するための管理として、「中庸」すなわち「バランス」の重要性を主張したのです。
第2ステージは、E.メイヨーらの「人間関係論(ヒューマン・リレーションズ)」です。これは、まさに科学的に合理性を探求しようとする「科学的管理法」に対して、働く者の心理や働く者同士の関係の充実を図ることこそ生産性の向上に資するものであると主張します。行動の背後にある人間心理にメスを入れたと言ってもよいでしょう。これを「人間探求の時代」(おおよそ1920年代から30年代)と呼ぶことにしましょう。このころ「組織論」が産声をあげます。ちなみに、この人間関係論を足掛かりにして、のちにモチベーション論やリーダーシップ論が開花することとなり、この理論グループは行動科学的アプローチなどと称されるようになります。
第3ステージは、H.A.サイモンの論に端を発する「意思決定論」です。それ以前の経営学の主眼は、実施の側面に焦点を当ててきました。つまり、行動を合理化することであるべき姿を実現しようというわけです。これに対して、サイモンはどんな行動にもそれに先立つ意思決定過程が存在することに着目し、この意思決定のプロセスをマネジメントすることで行動も合理化されると考えました。これを「決定探求の時代」(おおよそ20世紀半ば以降)と呼ぶことにしましょう。そしてほぼ同時期に「戦略論」が耳目を集めるようになります。
第4ステージは、ローレンス=ローシュらによって精緻化された「環境適応の論理」です。それ以前の考え方は専ら経営の内部構造に焦点を当て、そのマネジメントの善し悪しを論じていましたが、それにもまして組織にとって重要なのは、取り巻く外部環境に適応することであると主張しました。これを機に、内部環境重視のクローズドシステム・アプローチから外部環境重視のオープンシステム・アプローチへと経営の基本スタンスが変わることとなりました。これを「適応探求の時代」(おおよそ1960年代以降)と呼ぶことにしましょう。ちなみに、この外部環境重視のスタンスは、経営戦略論のポジショニング・ビュー(自社に有利な環境を見出してそこに位置取り、有利な戦い方をすること)へと展開していくことにもなります。
第5ステージは、J.B.バーニーによる功績が大きい「経営資源論」です。外部環境重視の「環境適応の論理」に対して、成功のカギは他よりも優れた経営資源を構築することで、たとえ厳しい環境下においても有利に展開することができると主張します。例えば、厳しいアメリカ市場の様々な分野で、既存企業を次々と凌駕していったかつての日本企業の技術力やマンパワーといった優秀な資源保有がこれを雄弁に物語っています。これを「資源探求の時代」(おおよそ1980年代以降)と呼ぶことにしましょう。ちなみに、この内部資源重視のスタンスは、経営戦略論のリソース・ベースト・ビュー(資源こそ競争優位の源泉との見方)に相当するものです。
第6ステージは、稀有な「日本発」の理論である「知識創造論」です。これは野中郁次郎氏が理論的支柱となり精緻化されたもので、第5ステージの資源論との関連性が見出せる考え方です。経営資源の中でもとりわけ知識(情報的資源)こそ競争優位の源泉であり、組織とは個々人のぼんやりとした知恵のようなもの(暗黙知)を、様々なプロセスを経て集団や組織の知識(形式知)と呼べるものへと変換することを繰り返すことで他よりも優れた知識を確立することが何より重要であると考えます。これを「知識探求の時代」(おおよそ1990年代以降)と呼ぶことにしましょう。
少々お堅い話になってしまいましたね。さまざまな捉え方がありますが、経営学約140年の歴史のうち超メジャーなテーマを超ハイスピードで振り返るとこのようになるでしょう。簡単に、効率→人間→決定→適応→資源→知識と考えてよいと思います。
ひるがえって、現代社会はますます混沌としてきており、今後もその闇はいっそう深くなっていくように思えませんか。これと連動して経営環境もさらに曖昧模糊となっていくことでしょう。このような状況下で企業はどのようにして存続と成長を図っていくのかが最大のテーマとなります。そして経営学にはそのためのヒントを提供することが期待されていると言えます。また、私たち一人ひとりもこうした状況下に置かれることは免れないのです。経営学は企業に対してヒントを提供するだけにとどまらないと思っています。経営学を学習し理解することで、私たちもまた何某かの生きるためのヒントが得られるのではないかと確信しています。その意味で経営学は「人生学」とも言えると思います。
最後に、必要多様性の法則(アシュビーの法則)というものがありますが、これは「環境の多様性に対処するには組織も多様にならなくてはならない」という趣旨の意味です。ということは、組織(や個人)も多様にならなくてはならないということを示唆しているわけですが、それはたとえば、「とにかくやってみるしかない」、「常識に拘泥されず一見バカげたように思えることも拾い上げよ」、といったことも含意しているのではないでしょうか。アップル(リンゴではなく会社)の創業者経営者であった故スティーブ・ジョブズ氏も意識していた言葉に「stay hungry,stay foolish(貪欲さを失うな、愚かであることも大事だ)」というものがありますが、このようなことと併せて考えると彼が何故この言葉を意識していたのかが分かるような気がしますね。
学生時代から経営学を学習してきましたが、最初の産能との出会いは短期大学でした。それは今から27年ほど前に遡ります。私もまだ若く少年の面影を残していたに違いないでしょう。「あれから40年」、いや27年ですが、今では残酷な時の彫刻によって見事なオヤジへと変貌を遂げました。それはさておき、短大では若い学生さんはもちろん、社会人学生の方も多く学ばれており、多くのことを共に学ばせていただいたと思っています。
そしてその翌年から、通信教育課程(大学・短大)でお世話になるようになり、それまで以上に社会人の学生さんを中心に授業を行うようになりました。爾来、通信教育課程でも26年間、「文武両道」ならぬ「文勤両道」(勝手な造語ですが勉強と仕事の両立の意)を目指す学生さん、そして献身的にサポートしてくださる事務部の方々、みなさんのおかげで現在まで続けてこられたと感謝しております。私の心身共に「MADE IN SANNO」と言えると思います。
私の身の上話などはこのへんにして、経営学関連を学ぶ学生さんも多いと思いますので、次に少々真面目に経営学の歴史を彩ったその時々の主要なテーマを超コンパクトに概観してみたいと思います。
近代経営学(アメリカ経営学)の本格的な萌芽はF.W.テイラーの「科学的管理法」に見出せると言われています。これは、当時の工場でのいい加減な「成り行き的な管理」から脱却するために、工場での仕事を科学的に分析し作業者に割り当てることで、ムダをなくし生産性を向上させようということに主眼が置かれます。これを「効率探求の時代」(おおよそ19世紀終わりから20世紀初頭)と呼ぶことにしましょう。これが第1ステージで「管理論」から経営学はスタートしました。
ちなみに、わが国における「マネジメント」思想の始祖は本学の創立者上野陽一先生です。先生は海の向こうの「科学的管理法」の思想にインスパイヤ—され、その考え方をさらに日本流に発展させ「能率学」として日本マネジメント界の原点を開花させました。そして、管理の理想形として、ムダもムリもないムラのない状態、明確な目的とそれに適合した手段がとられている状態、持ち前が100%発揮されている状態、などに着目しました。すなわち、能率を実現するための管理として、「中庸」すなわち「バランス」の重要性を主張したのです。
第2ステージは、E.メイヨーらの「人間関係論(ヒューマン・リレーションズ)」です。これは、まさに科学的に合理性を探求しようとする「科学的管理法」に対して、働く者の心理や働く者同士の関係の充実を図ることこそ生産性の向上に資するものであると主張します。行動の背後にある人間心理にメスを入れたと言ってもよいでしょう。これを「人間探求の時代」(おおよそ1920年代から30年代)と呼ぶことにしましょう。このころ「組織論」が産声をあげます。ちなみに、この人間関係論を足掛かりにして、のちにモチベーション論やリーダーシップ論が開花することとなり、この理論グループは行動科学的アプローチなどと称されるようになります。
第3ステージは、H.A.サイモンの論に端を発する「意思決定論」です。それ以前の経営学の主眼は、実施の側面に焦点を当ててきました。つまり、行動を合理化することであるべき姿を実現しようというわけです。これに対して、サイモンはどんな行動にもそれに先立つ意思決定過程が存在することに着目し、この意思決定のプロセスをマネジメントすることで行動も合理化されると考えました。これを「決定探求の時代」(おおよそ20世紀半ば以降)と呼ぶことにしましょう。そしてほぼ同時期に「戦略論」が耳目を集めるようになります。
第4ステージは、ローレンス=ローシュらによって精緻化された「環境適応の論理」です。それ以前の考え方は専ら経営の内部構造に焦点を当て、そのマネジメントの善し悪しを論じていましたが、それにもまして組織にとって重要なのは、取り巻く外部環境に適応することであると主張しました。これを機に、内部環境重視のクローズドシステム・アプローチから外部環境重視のオープンシステム・アプローチへと経営の基本スタンスが変わることとなりました。これを「適応探求の時代」(おおよそ1960年代以降)と呼ぶことにしましょう。ちなみに、この外部環境重視のスタンスは、経営戦略論のポジショニング・ビュー(自社に有利な環境を見出してそこに位置取り、有利な戦い方をすること)へと展開していくことにもなります。
第5ステージは、J.B.バーニーによる功績が大きい「経営資源論」です。外部環境重視の「環境適応の論理」に対して、成功のカギは他よりも優れた経営資源を構築することで、たとえ厳しい環境下においても有利に展開することができると主張します。例えば、厳しいアメリカ市場の様々な分野で、既存企業を次々と凌駕していったかつての日本企業の技術力やマンパワーといった優秀な資源保有がこれを雄弁に物語っています。これを「資源探求の時代」(おおよそ1980年代以降)と呼ぶことにしましょう。ちなみに、この内部資源重視のスタンスは、経営戦略論のリソース・ベースト・ビュー(資源こそ競争優位の源泉との見方)に相当するものです。
第6ステージは、稀有な「日本発」の理論である「知識創造論」です。これは野中郁次郎氏が理論的支柱となり精緻化されたもので、第5ステージの資源論との関連性が見出せる考え方です。経営資源の中でもとりわけ知識(情報的資源)こそ競争優位の源泉であり、組織とは個々人のぼんやりとした知恵のようなもの(暗黙知)を、様々なプロセスを経て集団や組織の知識(形式知)と呼べるものへと変換することを繰り返すことで他よりも優れた知識を確立することが何より重要であると考えます。これを「知識探求の時代」(おおよそ1990年代以降)と呼ぶことにしましょう。
少々お堅い話になってしまいましたね。さまざまな捉え方がありますが、経営学約140年の歴史のうち超メジャーなテーマを超ハイスピードで振り返るとこのようになるでしょう。簡単に、効率→人間→決定→適応→資源→知識と考えてよいと思います。
ひるがえって、現代社会はますます混沌としてきており、今後もその闇はいっそう深くなっていくように思えませんか。これと連動して経営環境もさらに曖昧模糊となっていくことでしょう。このような状況下で企業はどのようにして存続と成長を図っていくのかが最大のテーマとなります。そして経営学にはそのためのヒントを提供することが期待されていると言えます。また、私たち一人ひとりもこうした状況下に置かれることは免れないのです。経営学は企業に対してヒントを提供するだけにとどまらないと思っています。経営学を学習し理解することで、私たちもまた何某かの生きるためのヒントが得られるのではないかと確信しています。その意味で経営学は「人生学」とも言えると思います。
最後に、必要多様性の法則(アシュビーの法則)というものがありますが、これは「環境の多様性に対処するには組織も多様にならなくてはならない」という趣旨の意味です。ということは、組織(や個人)も多様にならなくてはならないということを示唆しているわけですが、それはたとえば、「とにかくやってみるしかない」、「常識に拘泥されず一見バカげたように思えることも拾い上げよ」、といったことも含意しているのではないでしょうか。アップル(リンゴではなく会社)の創業者経営者であった故スティーブ・ジョブズ氏も意識していた言葉に「stay hungry,stay foolish(貪欲さを失うな、愚かであることも大事だ)」というものがありますが、このようなことと併せて考えると彼が何故この言葉を意識していたのかが分かるような気がしますね。
こうしたことと関連するかもしれませんが、右の写真は、私が(AKBではなく)AKO(Alone Kara Oke)と呼ぶ余興です。いわゆる一人カラオケです。


いま一つは、たまに一人でダラダラ歩いたり走ったりすることです。愚かになることがいかに大変かを常々感じています。
みなさんの本学通信教育課程での学びが充実したものになることを願っています。
SANNO(。・ω・。)ノ♡