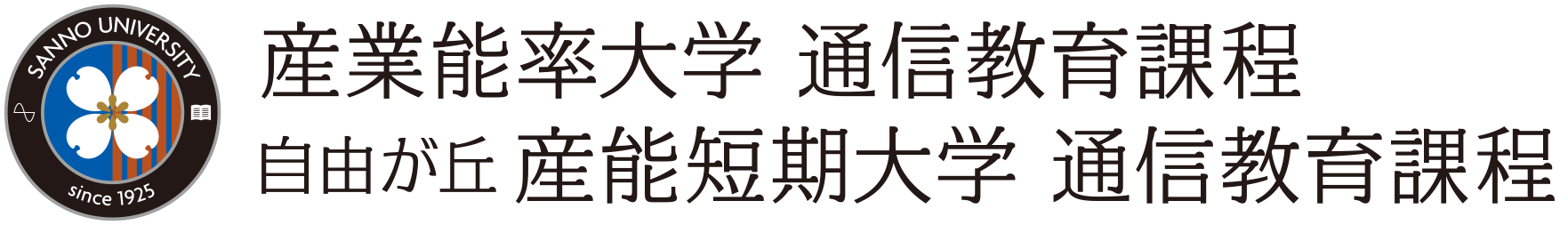リレーエッセイ 2020.11

末﨑 裕康 (Hiroyasu Massaki)
<担当科目>
「心理療法」「人間関係を学ぶ心理学」他
<趣味、特技>
家事、音楽鑑賞
<メッセージ>
自分を成長させるにはどうすればよいでしょうか?
様々な成長の形がありますが、成長を「“自分の枠”を拡げること」とシンプルに考えたとき、「やったことのないことをやるとよい」という答えになります。…と言われると大掛かりなことのように聞こえますが、「本学に入学した」という点でみなさんの成長はすでに始まっているのです。すばらしいですね!
「成長」し続けているみなさんとお会いできる日を楽しみにしています!
「心理療法」「人間関係を学ぶ心理学」他
<趣味、特技>
家事、音楽鑑賞
<メッセージ>
自分を成長させるにはどうすればよいでしょうか?
様々な成長の形がありますが、成長を「“自分の枠”を拡げること」とシンプルに考えたとき、「やったことのないことをやるとよい」という答えになります。…と言われると大掛かりなことのように聞こえますが、「本学に入学した」という点でみなさんの成長はすでに始まっているのです。すばらしいですね!
「成長」し続けているみなさんとお会いできる日を楽しみにしています!
「自信」ってなに?
あなたは「自信」がありますか?
あなたは「自信」がありますか?
私は本学に入職するまで、主に教育現場や医療現場などでカウンセラーという役割で働いてきました(今も細々と続けていますが)。その中でしばしば耳にしたのが「自信」という言葉です。例えばスクールカウンセラーとして勤務していた中学校では、学校に通えている子でも通えていない子でも“自信がない”と評価される生徒は多く、成績が良くなかったり、部活動で良いパフォーマンスを上げられなかったり、友達関係でトラブルが起こったり、様々な問題(とみなされている)行動の原因として、この“自信のなさ”が指摘されていました。他方、中学生に限らず、家庭や職場、友人とのやり取りなど「自信」は私たちオトナの日常生活でもしばしば耳にする言葉です。そして“自分には自信がない”と自覚し、様々なトラブルの原因として考えている方も多いのではないでしょうか。
・・・でもちょっとまってください! そもそも「自信」とは何なのでしょうか!? そして“自信をつける”にはどうすればいいのでしょうか。今回のエッセイでは「自信」について心理学的観点から再確認し、また、「自信」を身につける方法について考えてみましょう。
私は本学に入職するまで、主に教育現場や医療現場などでカウンセラーという役割で働いてきました(今も細々と続けていますが)。その中でしばしば耳にしたのが「自信」という言葉です。例えばスクールカウンセラーとして勤務していた中学校では、学校に通えている子でも通えていない子でも“自信がない”と評価される生徒は多く、成績が良くなかったり、部活動で良いパフォーマンスを上げられなかったり、友達関係でトラブルが起こったり、様々な問題(とみなされている)行動の原因として、この“自信のなさ”が指摘されていました。他方、中学生に限らず、家庭や職場、友人とのやり取りなど「自信」は私たちオトナの日常生活でもしばしば耳にする言葉です。そして“自分には自信がない”と自覚し、様々なトラブルの原因として考えている方も多いのではないでしょうか。
・・・でもちょっとまってください! そもそも「自信」とは何なのでしょうか!? そして“自信をつける”にはどうすればいいのでしょうか。今回のエッセイでは「自信」について心理学的観点から再確認し、また、「自信」を身につける方法について考えてみましょう。
「自信」と「自己効力感」
「自信」という言葉を国語辞典で調べると、「自分で自分の能力や価値などを信じること。自分の考え方や行動が正しいと信じて疑わないこと。」※1と記されています。この意味に最も近い心理学の用語は「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」という言葉です。心理学の辞典には「自分が行為の主体であると確信していること、自分の行為について自分がきちんと統制しているという信念、自分が外部からの要請にきちんと対応しているという確信」※2 (下線は筆者)と記されています。例えば「私は誰も文句のつけようのないおいしい天津飯を作ることができる(という確信をもっている)」とか「私は誰もが納得するプレゼンテーションができる(という確信をもっている)」「私は初対面の人とすぐに打ち解けることができる(という確信をもっている)」などは“自己効力感が高い”と言うことができます。そして「~という確信を持っている」の部分が、いわゆる「自信」がある状態なのでしょう。
ここまでで分かったことは「自信」≒「自己効力感」という図式であり、従っていわゆる「自信」をもつためには自己効力感を得られるようなことをすればいい、と理解できます。ただ、ここで思い出されるのが、私たちは「自己肯定感」とか「自尊心」など、なんとなく似たような言葉も聞いたことがあるということです。せっかくなのでこれらの言葉についても調べてみましょう。
------------------------------
※1.『デジタル大辞泉』, 小学館
※2.中島ら編(1999), 『心理学辞典』, 有斐閣
ここまでで分かったことは「自信」≒「自己効力感」という図式であり、従っていわゆる「自信」をもつためには自己効力感を得られるようなことをすればいい、と理解できます。ただ、ここで思い出されるのが、私たちは「自己肯定感」とか「自尊心」など、なんとなく似たような言葉も聞いたことがあるということです。せっかくなのでこれらの言葉についても調べてみましょう。
------------------------------
※1.『デジタル大辞泉』, 小学館
※2.中島ら編(1999), 『心理学辞典』, 有斐閣
「自信」と「セルフ・エスティーム(自己肯定感)」
山崎(2017)※3 によれば、“自分に自信をもった心”は『自尊感情』や『自尊心』、『自己肯定感』などと言われ、英語で言えば「セルフ・エスティーム[self-esteem]」という言葉なのだそうです。もとはアメリカで研究が始まり、それが日本に紹介されるときに様々な訳語が当てられた経緯があるようです。「セルフ・エスティーム」は感情だけでなく認知、態度、行動など心理的な特徴をすべてカバーするもので、そのため性格としての概念であることが指摘されています※3。・・・あれ? 「自己効力感」と何が違うの? “自己肯定感が低い”って “自分に自信がない”っていう意味じゃないの? と聞こえてきますね。実は、「セルフ・エスティームとしての自己肯定感」と「自信(自己効力感)」は意味として重なる部分もありますが、大きく異なる部分もある別個の概念なのです。そして驚くべきことに、自己肯定感が、良好な日常生活を送るための様々な変数(心身の健康、適応力など)に良い影響を及ぼすという“常識的な考え”を否定する研究結果も発表されています※4。とすると、日常生活での様々なトラブルの原因を自己肯定感の低さに求めることはお門違いなのかもしれません。
------------------------------
※3.山崎勝之(2017), 『自尊感情革命 なぜ、学校や社会は「自尊感情」がそんなに好きなのか?』, 福村出版
※4.Baumeister, R. F. et al., (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science In The Public Interest, 4, Pp.1-44
------------------------------
※3.山崎勝之(2017), 『自尊感情革命 なぜ、学校や社会は「自尊感情」がそんなに好きなのか?』, 福村出版
※4.Baumeister, R. F. et al., (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science In The Public Interest, 4, Pp.1-44
「自己効力感」と「セルフ・エスティーム(自己肯定感)」
セルフ・エスティームという単語を改めて心理学辞典で確認すると、「自己に対する評価感情で、自分自身を基本的に価値あるものとする感覚。(後略)」2(下線は筆者)と記されており、一見すると「自己効力感」や「自信」と同じような意味に思えます。でもここで気をつけなければならないのが、「自分自身を基本的に価値のあるもの」という言葉です。これは何かが優れているとか、うまくできるとか、知識があるなどといった自己効力感を高くする要因はもちろんですが、反対に何かが劣っているとか、うまくできないとか、知識がないといった自己効力感を低くする要因も含んでいるのです。つまり「自己効力感を高くする要因にせよ低くする要因にせよ、それらを持っている自分自身を基本的に価値のあるものとして評価する感情」と言い換えることができます。込み入ってきたので具体例で考えてみましょう。
(1)は自己効力感を高くする要因、反対に(2)は自己効力感を低くする要因の例です。繰り返しますが自己肯定感は、いずれの場合でも“その要因を持っている自分を、良い悪いはともかく素直に自覚しているかどうか”が問題となります。この点をもう少し日常的な感覚に近い行為、「他人に素直に言えるか言えないか」で考えてみましょう。
この例(1)a.は理解しやすいと思います。問題なのはここからです。
(2)a.には失敗談や自虐ネタなども含まれるでしょう。自分のネガティブな側面について、(良し悪しは別にして)なんとも思ってないと言えるかもしれません(この場合の「ネガティブ」という評価は主観的なものです。もちろん「おいしい」も主観的な評価です)。
いわゆる「自信のない人」は(2)b.の振る舞いが多いのではないでしょうか。
(1)b.のような人は実際にはあまりいないでしょう。謙遜した表現はあっても、(2)b.のような振る舞いではないと思います。
このように、自己肯定感と自己効力感を別軸の概念ととらえると、それぞれの高低の組み合わせを考えることができます。そして一般的な意味で“自信がない”あるいは“自己肯定感が低い”と言われる状況は(2)b.の場合ということも浮かび上がってきました。この例を使ってもう少し掘り下げてみましょう。おいしい天津飯を作ることができない自分について素直に言えない(=「自己肯定感が低い」)とのはどういう状況でしょうか。それは、「おいしい天津飯を作ることができない自分を何らかの理由で受け容れられない状況」ということができます。ではなぜ、おいしい天津飯を作ることができない自分を受け容れられないのでしょうか。ここまでくるとその人個人が抱える過去によるため一概には言えません。そこで例から離れてもう少し一般化した質問に言い換えてみましょう。
「○○」の内容によっては返答に困ってしまう、ずいぶんと切れ味の鋭い質問になってしまいました。でもここが、低い自己肯定感を高めるための入り口になります。一人ではしんどい作業ですので、信頼できる他者と一緒に深めるといいでしょう(カウンセラーでもいいですよ!)。
「おいしい天津飯を作ることができる自分」(1)
「おいしい天津飯を作ることができない自分」 (2)
「おいしい天津飯を作ることができない自分」 (2)
(1)は自己効力感を高くする要因、反対に(2)は自己効力感を低くする要因の例です。繰り返しますが自己肯定感は、いずれの場合でも“その要因を持っている自分を、良い悪いはともかく素直に自覚しているかどうか”が問題となります。この点をもう少し日常的な感覚に近い行為、「他人に素直に言えるか言えないか」で考えてみましょう。
(1)a. ある人が(1)を素直に言える場合
“「自己効力感が高い」かつ「自己肯定感が高い」”
“「自己効力感が高い」かつ「自己肯定感が高い」”
この例(1)a.は理解しやすいと思います。問題なのはここからです。
(2)a. ある人が(2)を素直に言える場合
“「自己効力感が低い」かつ「自己肯定感が高い」”
“「自己効力感が低い」かつ「自己肯定感が高い」”
(2)a.には失敗談や自虐ネタなども含まれるでしょう。自分のネガティブな側面について、(良し悪しは別にして)なんとも思ってないと言えるかもしれません(この場合の「ネガティブ」という評価は主観的なものです。もちろん「おいしい」も主観的な評価です)。
(2)b. ある人が(2)を素直に言えない場合
“「自己効力感が低い」かつ「自己肯定感が低い」”
“「自己効力感が低い」かつ「自己肯定感が低い」”
いわゆる「自信のない人」は(2)b.の振る舞いが多いのではないでしょうか。
(1)b. ある人が(1)を素直に言えない場合
“「自己効力感が高い」かつ「自己肯定感が低い」”
“「自己効力感が高い」かつ「自己肯定感が低い」”
(1)b.のような人は実際にはあまりいないでしょう。謙遜した表現はあっても、(2)b.のような振る舞いではないと思います。
このように、自己肯定感と自己効力感を別軸の概念ととらえると、それぞれの高低の組み合わせを考えることができます。そして一般的な意味で“自信がない”あるいは“自己肯定感が低い”と言われる状況は(2)b.の場合ということも浮かび上がってきました。この例を使ってもう少し掘り下げてみましょう。おいしい天津飯を作ることができない自分について素直に言えない(=「自己肯定感が低い」)とのはどういう状況でしょうか。それは、「おいしい天津飯を作ることができない自分を何らかの理由で受け容れられない状況」ということができます。ではなぜ、おいしい天津飯を作ることができない自分を受け容れられないのでしょうか。ここまでくるとその人個人が抱える過去によるため一概には言えません。そこで例から離れてもう少し一般化した質問に言い換えてみましょう。
「○○という問題を抱える自分を受け容れられないのはなぜでしょうか?」
「○○」の内容によっては返答に困ってしまう、ずいぶんと切れ味の鋭い質問になってしまいました。でもここが、低い自己肯定感を高めるための入り口になります。一人ではしんどい作業ですので、信頼できる他者と一緒に深めるといいでしょう(カウンセラーでもいいですよ!)。
「自信」を身につける方法
最後に、コラムのはじめに掲げた目的「『自信』を身につける方法」について改めて確認していきましょう。
まず、いわゆる「自信」は「自己効力感」と同じような意味と理解してよさそうなので、“物事をうまく進めることができるという確信を持てるようになること”を目指せばいいということになります。回りくどい表現になってしまいましたが、一言で言うと練習・努力あるのみです。才能や向き不向きなども影響するかもしれませんが、練習と才能の関係については様々な名言があるので興味がわいた方は調べてみてください(エジソンのものなど、どちらも同じくらい大事と言われているものが多くあるようです)。
そして「自己肯定感」と「自己効力感」は分けて考えるべき概念ということもわかりました。「自信」「自己効力感」と似たような意味としての「自己肯定感」の用法が世間一般に浸透していますが、広義の場合は練習あるのみということも確認できました。一方、狭義の自己肯定感を上げたい場合、自分自身を理解するという、つらくてしんどい作業が必要なようです。一方でそのような重々しいレベルではなく、軽やかなレベルでも自己理解はできます※5。これらを踏まえてまとめると、軽やかな部分も重々しい部分も、良い部分も悪い部分もひっくるめて今現在の自分であることを否定も肯定もせず「そんなものか」ととりあえず理解する、という作業が狭義の自己肯定感を高める作業と言えます。そしてもし気に入らない部分があるなら、その部分を変化させればいいだけのことですね。
------------------------------
※5.私の場合は、まさに今体験していることを言語化すると、一旦物書きを始めたら表現が回りくどくてしかも長文になる、〆切が近づかないと行動しない、書き始めたら止まらなくなって目安の分量を大幅に越えている、サボり癖がある、夕方以降でないと頭が働かない、こだわりが強い、ねむい、(2)a.が多い(自己効力感は低いんだなぁ)、天津飯が好き!・・・というふうに、自分について再確認した部分と新しく知った部分とが混在しています。
まず、いわゆる「自信」は「自己効力感」と同じような意味と理解してよさそうなので、“物事をうまく進めることができるという確信を持てるようになること”を目指せばいいということになります。回りくどい表現になってしまいましたが、一言で言うと練習・努力あるのみです。才能や向き不向きなども影響するかもしれませんが、練習と才能の関係については様々な名言があるので興味がわいた方は調べてみてください(エジソンのものなど、どちらも同じくらい大事と言われているものが多くあるようです)。
そして「自己肯定感」と「自己効力感」は分けて考えるべき概念ということもわかりました。「自信」「自己効力感」と似たような意味としての「自己肯定感」の用法が世間一般に浸透していますが、広義の場合は練習あるのみということも確認できました。一方、狭義の自己肯定感を上げたい場合、自分自身を理解するという、つらくてしんどい作業が必要なようです。一方でそのような重々しいレベルではなく、軽やかなレベルでも自己理解はできます※5。これらを踏まえてまとめると、軽やかな部分も重々しい部分も、良い部分も悪い部分もひっくるめて今現在の自分であることを否定も肯定もせず「そんなものか」ととりあえず理解する、という作業が狭義の自己肯定感を高める作業と言えます。そしてもし気に入らない部分があるなら、その部分を変化させればいいだけのことですね。
------------------------------
※5.私の場合は、まさに今体験していることを言語化すると、一旦物書きを始めたら表現が回りくどくてしかも長文になる、〆切が近づかないと行動しない、書き始めたら止まらなくなって目安の分量を大幅に越えている、サボり癖がある、夕方以降でないと頭が働かない、こだわりが強い、ねむい、(2)a.が多い(自己効力感は低いんだなぁ)、天津飯が好き!・・・というふうに、自分について再確認した部分と新しく知った部分とが混在しています。